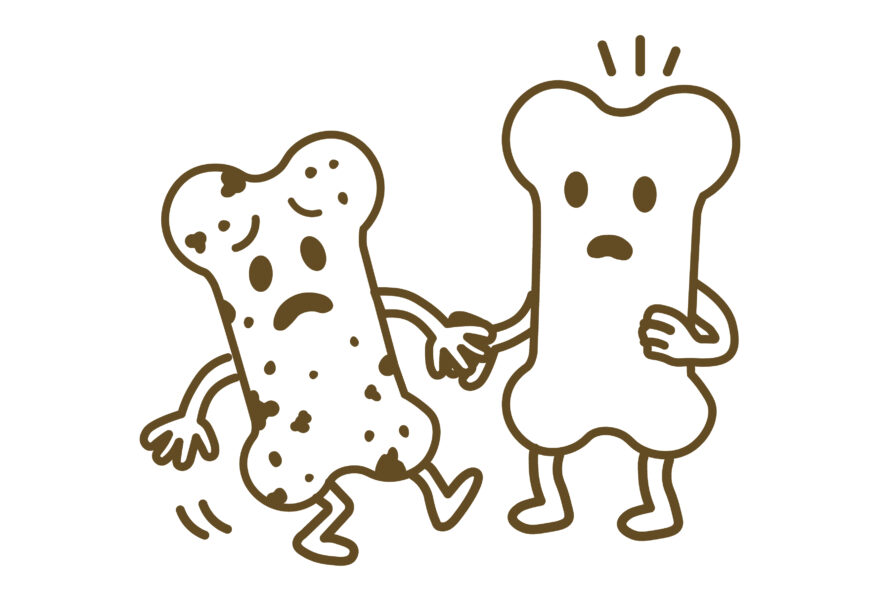 歯科コラム
歯科コラムはじめに
近年、加齢やホルモンバランスの変化により骨粗鬆症を患う方が増えており、同時に高齢者層を中心にインプラント治療を希望される患者様も増加傾向にあります。インプラント治療は、咀嚼機能や審美性の回復に優れている一方で、骨の健康状態に大きく依存する治療法でもあります。そのため、骨粗鬆症の治療を受けている方がインプラント治療を検討する際には、特有のリスクや注意点を正しく理解することが必要です。
今回、骨粗鬆症とインプラント治療の関係、治療薬の影響、注意点や対策、そして医師との連携の重要性について詳しく解説いたします。
1. 骨粗鬆症とは何か?
骨粗鬆症とは、骨密度が低下し、骨がもろくなる病気です。特に女性は閉経後のホルモンバランスの変化により、骨量が急激に減少する傾向があります。骨粗鬆症になると骨折のリスクが高まるほか、歯槽骨(歯を支える骨)にも影響が及ぶため、歯科治療にも支障をきたすことがあります。
2. インプラント治療における骨の役割
インプラント治療は、歯を失った部分の顎骨に人工歯根(インプラント体)を埋入し、その上に人工の歯を装着する治療です。インプラントが安定して機能するためには、十分な骨量と骨密度が必要です。
骨粗鬆症によって骨が脆弱になっている場合、インプラントが骨と結合(オッセオインテグレーション)しにくくなり、治療の成功率が下がる可能性があります。
3. 骨粗鬆症治療薬とインプラント治療の関
骨粗鬆症の治療には、以下のような薬剤が使われることがあります。
ビスホスホネート(BP)製剤
- ・骨吸収を抑えることで骨密度を保つ薬。
- ・長期間の使用により「顎骨壊死(がっこつえし)」という重篤な副作用を引き起こすリスクがある。
- ・抜歯やインプラント手術後に発症しやすいため、治療歴の確認が必須。
デノスマブ(抗RANKL抗体)
- ・骨吸収を抑える注射薬。BPと似たリスクがある。
- ・投与中断時の骨折リスクや、手術時の骨治癒遅延に注意。
その他(ホルモン製剤、ビタミンDなど)
・リスクは比較的低いが、総合的に医師の判断が求められる。
4. インプラント治療前のチェックポイント
1. 現在および過去の治療歴の把握
- どの薬剤を、どのくらいの期間使用していたかを正確に申告。
2. 骨密度の評価
- 顎骨のCT検査やDEXA法による骨密度測定を行い、骨の状態を把握。
3. リスクとベネフィットのバランス
- インプラント以外の治療法(ブリッジや義歯)との比較検討も行う。
4. 主治医との情報共有
- 内科・整形外科の主治医と歯科医師の間で連携を図る。
5. インプラント治療中および治療後の注意点
- ・術後の感染予防:顎骨壊死のリスクを避けるため、衛生管理を徹底。
- ・定期的な経過観察:骨の状態やインプラントの安定性を継続的に確認。
- ・薬剤の調整・中止についての判断:投薬中断の可否は医師による総合判断が必要。
・自己判断の禁止:薬を自己判断で中止することは絶対に避ける。
6. ケーススタディ
ケースA:ビスホスホネート内服中の70代女性
- ・数年前から骨粗鬆症治療を受けており、BP製剤を5年以上内服。
- ・顎骨の状態は良好であり、投薬の一時中断(ドラックホリデー)を整形外科医と協議。
- ・術前・術後に抗生物質を使用し、慎重にインプラント治療を実施。
- ・結果、インプラントは良好に機能。
ケースB:デノスマブ使用中の60代男性
- ・半年ごとに皮下注射を受けており、インプラント希望。
- ・骨の代謝状態を血液検査で評価。
- ・歯科医と内科医が情報共有し、最適な治療タイミングを調整。
・インプラント治療を延期し、先に義歯で対応。後日、治療実施。
7. まとめ
骨粗鬆症の治療を受けている患者様がインプラント治療を行う際には、単に歯科的な視点だけでなく、全身の健康状態や薬物療法との関係を十分に考慮する必要があります。特にビスホスホネート製剤やデノスマブを使用している場合は、顎骨壊死という重篤なリスクを伴うため、専門的な判断と慎重な治療計画が求められます。
信頼できる歯科医師と内科・整形外科医との連携を保ちながら、安全かつ効果的な治療を目指すことが重要です。
